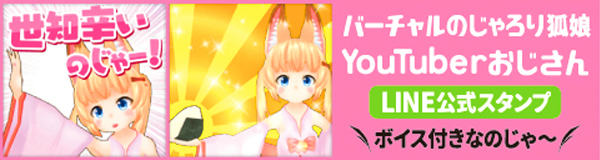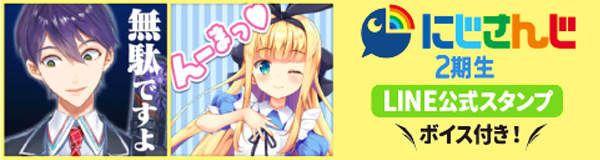ゲームセンターに外からイノベーションを バンナム、小山氏・田宮氏が語る「VR ZONE」への想い

ナムコとバンダイナムコエンターテイメントは15日、東京のお台場にVRアミューズメント施設の「VR ZONE Project i Can」をオープンさせた。6種類あるコンテンツのうち、5つはHTC Viveをかぶり、体感筐体に乗って「あちらの世界」を存分に堪能できるものとなっている(ニュース記事)。
いったいどんなコンセプトでこの企画が立ち上がって、オープンまでこぎつけたのか。VR ZONEを手がけた、バンダイナムコエンターテインメントの小山順一朗氏と田宮幸春氏にインタビューしたところ、実は「ギャラクシアン3」や「戦場の絆」などの時代から積み重ねてきたノウハウが集結しているという面白い話を聞けた。ほぼノーカットでまとめたので、ぜひ全文読んでいただきたい。

写真右より、「コヤ所長」ことバンダイナムコエンターテインメント 執行役員 AM事業部 エグゼクティブプロデューサーの小山順一朗氏、「タミヤ室長」ことAM事業部の田宮幸春氏。小山氏は「機動戦士ガンダム 戦場の絆」や「アイドルマスター」など、田宮氏は「ドラゴンボール ZENKAIバトルロイヤル」など、数々のアーケードゲームを手がけてきた人物になる。
*小山氏、田宮氏も出演するトークイベント「Tokyo VR Meetup #04 VR×ネカフェ・アミューズメント施設の可能性」を4月28日に開催します。ぜひご参加ください。
Oculus RiftのDK1で「戦場の絆」を試していた
——VR ZONEを体験させていただきましたが、これだけVR推しのエンターテイメント施設というと、90年代のVRブーム以来なかったのではないでしょうか?
小山 そうですね。まずバーチャルという言葉の意味が難しくて、日本だと「疑似」や「コンピューターの偽物」と同義になってしまってるじゃないですか。「それってバーチャルじゃない?」という言い方をしてしまったり。バーチャルマネーもそうで、本当は実質的なお金なのに、イメージ的には贋金的な印象を持ってしまう人も多い。北米では全然意識が違っていて、実質的な体験を提供してくれる機械と思ってくれます。
——確かにお言葉の通りで、「スキーロデオ」ではスキー場を滑る、「アーガイルシフト」も巨大ロボットに乗るという体験を実質的に提供してくれた印象でした。

雪山を猛スピードで急滑降する「スキーロデオ」。体感筐体のスキー板に乗り、左右にエッジを効かせて進行方向を制御してゴールを目指す。

「アーガイルシフト」は、アンドロイドの少女とともにコックピットに乗り込んで、巨大ロボットを操って戦うシチュエーション。「男の子」の夢をまさに体現したVRコンテンツだ。
——このプロジェクトはいつ頃から始められたのでしょうか?
小山 1年ぐらい前ですね。
田宮 でも本当に動き出したのは、昨年の夏前ぐらいからで、コンテンツも一気に全部立ち上げています。
小山 本気で取り組み始めたのは9月ぐらい? 最初にやろうと言っていたときには「小山ンランド」とかいう名称もあって、ちょっと馬鹿にされていたんですよ。
——(爆笑)
田宮 「小山エキスポ」と呼ばれていましたね。
——「小山エキスポ」でもいいじゃないですか!!
小山 いやいやいや。でも馬鹿にされていた中で、田宮と柳下(AM事業部 企画開発1部 ゼネラルマネージャー 柳下邦久氏)は一緒にやろうと言ってくれた。
——原田さん(「鉄拳」シリーズや「サマーレッスン」のプロデューサーであるバンダイナムコエンターテインメントの原田勝弘氏)も過去の講演で言っていたように、やはり社内ではいろいろとお金の話が出てくるわけですよね。
小山 そうですね。VRって言ってみれば40歳以上の人は「アレでしょー?」みたいな感覚があるんです。グループインタビューで、「バーチャルリアリティーの○○です」という話をすると、みなさん「やったことあるよ! 家電量販店に置いてあるアレでしょ!」と、普通のヘッドマウントディスプレーや3Dメガネと勘違いしてしまう。
田宮 VR ZONEで採用しているHTC Viveも、装着するときに個人シアターと勘違いされる方も多いんです。
小山 VRという言葉の捉え方も、「Second Life」(日本では2007年に流行した3Dオンラインコミュニケーションツール)を経験された若い方とも違うと思うんですよね。
——トラウマじゃないですけど、世代によっていろいろなVRに対する期待と失望があったのかもしれないですね。
田宮 そういう意味では、われわれもVRという言葉を使うかどうかも悩んだところなんです。新しい用語を作ったほうがいいのかどうかと散々議論しました。ただ昨今の流れで行くと、おそらく新しいイメージで捉えてくれるかなということで、あえてVRで今回は行ってみようということになりました。それぐらい言葉には葛藤があった感じです。
——「VR ZONE Project i Can」という名前の由来は?
小山 もともとは「Project i Can」ということで、「大人ができなかったことをやる」という気持ちを込めて、草の根的な研究チームとして動いていたのと、もうひとつバンダイナムコスタジオと仲間が分かれていたので、彼らはそういうのが大好きな人間なので声をかけたら「やりたい!」と言って話が動いていたからです。
VRという点では、3年ほど前にOculus RiftのDK1(初代開発キット)に触ったのがきっかけでした。堤くんという、技術畑で先端性あふれる機器への関心が高い社員がいて、Oculus VRのパルマー・ラッキー氏から直接機材を借りて持ってきてくれたので、「機動戦士ガンダム 戦場の絆」(ドームスクリーン型筐体の対戦ゲーム)を移植してみたんです。そうしたら、そのままの体験だった(笑)

Oculus RiftのDK1。2013年春ごろに出荷が始まった。
——(笑)。従来のドームシアターと代わり映えが何もなかったと。
小山 ホワイトベースの中で、後ろにガンキャノンがいるのがわかったのは覚えています。パイロットスーツの手も動かせるようにしていたのですが、結局、ドームスクリーンでもVRとしてつくっていたので体験は同じだなと。
——ドームスクリーンもゴーグルではないVRですよね。
小山 あとはガンダムのコックピットって、モニターじゃないですか。だから頭の位置を動かしても、外の景色もズレない。そういう設定でつくっているので、(外部カメラによるポジショントラッキングがないDK1でも)そのままでした。そのときに感じたのは、「ロックオンがより手軽になって、世界一簡単なFPSができるな」と。
DK1はそこ止まりだったのですが、その後、Project Morpheus(PlayStation VRの開発コードネーム)を見に行ったときに発表前の「DRIVECLUB」を触って、「こんなに解像度も上がってるし、これは面白くなるぞ」と直感して、原田も「サマーレッスン」をつくるようになるわけです。

多くの人を魅了して、生ける伝説ともいえる存在になった「サマーレッスン」(レビュー記事)。
小山 最初は「スキーをやってみない?」といった話もしていましたが、多分酔うし、ひとつの部屋の中を再現したほうが注目度も上がりそう。ということで「サマーレッスン」をきっちり作り込んだところ、いったんは「VRといえばバンダイナムコゲームス」という評判をつくることができました。
でもその後、他社さんからいろいろなVRタイトルが出てきてしまったので、「田宮くん、これは私たちも動かなければいけませんな」という話をしていた。
田宮 去年の4、5月にそんな話をしてましたね。最初はコンセプトとしてきれいにまとまっていませんでしたが、ちょっとずつ贅肉が取れていって、最終的にVRで「大人のできなかったことをやる」というところで勝負しようと整っていった流れですね。
「ギャラクシアン3」時代から続く研究
小山 もうひとつ決まっていたのは「メカ(アーケード筐体)と組み合わせよう」という話です。
田宮 メカがわれわれの強みで、他社さんがいきなりやろうと思ってもできないところですので。
小山 油圧シリンダーを使った筐体制御は、それこそ「ギャラクシアン3」(1990年にお披露目された最大28人で遊べる体感型シューティング)からやってましたから。ドーナツみたいな状態になっていて、中央に当時、飛行機にしか使われていなかった3管プロジェクターを外側に向けて16台、円筒状に並べました。その周囲のシートにプレイヤーが座り、さらに外側の360度スクリーンに映像が映し出されます。
ギャラクシアン3では、映像に合わせてモーションシートもついてくるように、フロア全体を油圧機構で動かしていたんです。当時、体感型筐体といえば、だいたい50インチのプロジェクターが置いてあって、スキーや車が題材のことがほとんどでした。そんな20年以上も前からゴーグルではないVRをやってきた。
だから映像と筐体を一緒に動かすとその世界にいるという感覚が強まることがよくわかっていたため、「予算があったらな……」という思いはずっとありました。
——すごい。20年もの積み重ねがあったわけですね。

VR ZONEで体感できるうち、アーガイルシフト、トレインマイスター、リアルドライブの3つは同じ油圧シリンダー機構でシートを制御している。
小山 酔いの研究もずっとやっています。「戦場の絆」も最初にドームで囲ってみましたが、遊ぶとまぁ、気持ち悪くなる(笑)。ものすごい酔いでしたね。
田宮 最初はスゴかったですよね。
小山 目ん玉の後ろ側を掴まれてグリグリされているみたいな。
田宮 初期の「戦場の絆」は本当に乗れたもんじゃなかった。
——ドーム型スクリーンでも、VR酔いは発生しますよね。
小山 VRでは、「CAVE」といわれる多面のディスプレーに囲まれて体感できるものもありました。そもそもドームスクリーンも軍事用に開発されていたものがあって、それを「戦場の絆」では安価につくることに成功した。でもとにかく酔うわけで、その理由をつきつめていったときに、「ゲームとしてつくるからだ」ということに気づいたわけです。
カメラの制御がすごく大事。例えば、四角いディスプレー向けのゲームでは、車でブレーキを踏むと車体の後ろが上がって、アクセルを踏むと前が上がるといった演出をカメラを動かして表現するわけですが、それをドームスクリーンでやると、とんでもなく酔ってしまう。「これはやっちゃいけない。カメラは定点で見たままでしか映しちゃいけない」とわかりました。
そうすると今度は動いた感じがしないので、コックピットぐらいは動かそうと。いろいろやって手前のフレームだけ揺らして、外の風景は固定という方法だと酔わないことがわかりました。
田宮 「戦場の絆」の衝撃表現は、すべてフレームだけでやってます。それは昨今のVRコンテンツでもまったく同じことをやられていますよね。
——ここ半年ぐらいで、まさに同じVR酔いを低減させる手法の話が出てきてます。
小山 10年ぐらい前からやってます。
田宮 じゃないと「戦場の絆」は商品にならなかったですから。最初はペットの首につける「エリザベスカラー」や遮眼帯で、少しずつ周囲を見せていく手法も試していたりました。
——ハードもソフトも長年の試行錯誤があって、今のVR ZONEにつながっているわけですね。
小山 そうです。そこの知見があったんです。
高所の怖さを知っている人こそVRで歩けない
小山 ほかにも「スター・ウォーズ:バトルポッド」(ドームスクリーン型筐体のシューティングゲーム)も「戦場の絆」も架空の世界じゃないですか。人って、架空のものをVRと言われても、より現実的なものと比較しないと実感がわかないんです。「リアルドライブ」も車で表現したら「おお、本物みたいだ」と驚いてくれたので、車にしています。
「サマーレッスン」も宇宙空間とかじゃなくて、CGを作り込んで置き換えたほうが、リアリティーを感じられることがわかっていた。「バーチャル空間に入ったら火星に行ってみたい」みたいなのはナシねという話で進めていました。
田宮 「高所恐怖SHOW」も例えばスカイツリーの上とかをやってもいいんですが、むしろ現実感がなくなってしまうんです。いろいろ検証して、同じような高さでビルが建ってて、下に車が走ってるのが見える200mぐらいが一番怖く見えるというのがわかりました。

地上200mにエレベーターで移動して、突き出した板の上にいる猫を救出する「高所恐怖SHOW」。板が揺れて風が吹いてくるのがかなり怖い!!
小山 40mとかもやりましたよね。
田宮 高さをリアルに感じられるときに、怖さが出るんです。「高所恐怖SHOW」はもともとクレッセントさんが原案で、今回、アイデアをいろいろ足してつくらさせていただいたのですが、そのオリジナルのほうで、鳶職の方と自衛隊の落下傘部隊にいられた方だけが渡れなかったというお話を聞きいたことがあります。
——なんと!
田宮 高さの本当の怖さを知っている人なので、「命綱も何もない状態であんなところに立てるわけがない。無理です」と拒否されたそうです。逆に高いところにまったく行ったことがないデザイナーの女の子がスタスタ渡ってしまったりとか。
小山 以前、テレビの収録であったのですが、目隠しした状態で何をやるのかわからない状態の人を連れてきて、いきなり「高所恐怖SHOW」をやらせたところ、全然怖がらないんですよね。バーチャル空間に入ったという意識がないと、いきなり映像を見せられても頭がついてこない。まだまだ研究分野としては気づきが多いと思います。
——確かに。
小山 「高所恐怖SHOW」もエレベーターホールをVR ZONEに再現して、映像の中でエレベーターに乗って上がっていくのが体感できるようにする案もありました。でもそうではなく、全部見えて、友達がいてみんなで騒いでいる方が感動が変わってくるだろうと。
田宮 こうした体感ものは、やっている人が声を出してナンボだったりします。気持ちよく声を出せると、最終的に「楽しかったな」につながる。「高所恐怖SHOW」を一人でやらせると、静かにわたって、静かに帰ってくる方もいます。「怖くなかったのかな?」とゴーグルを外して感想を聞くと、「めちゃめちゃ怖かったです」と返されることも多いんです。
だったら友達も入れちゃって、チャチャを入れてくれた方がよっぽど楽しい。お一人の方には「大丈夫ですか? めちゃくちゃ膝が震えてますよ」と呼びかけていると、だんだん声を出してもらえるようになる。VRコンテンツというよりは、興行に近い演出ですね。
——それは重要な知見ですね。しかしVR ZONEは、ゲームセンターとも遊園地のようなアトラクションとも違う感覚ですね。
小山 遊園地のアトラクションは、どちらかというと受動的なところがあって、全員が同じ体験できるように設計されていますよね。ジェットコースターしかり、メリーゴーランドしかり。でもVR ZONEは挑戦して、失敗するという要素があるので、そうしたアトラクションとも違う。一方で、技術を突き詰めていくゲームセンターのゲームでもない。だから「VRアクティビティー」と呼んでいます。
田宮 能動的に、しかも体験を楽しんでもらいたいという思いを込めるために、言葉をギリギリまで調整していました。
——確かに 「高所恐怖SHOW」で猫を助けるという目的が達成できなかったとしても、体験の過程だけで非常に楽しいです。
小山 そうなんです。ゲームって、最初はユーザーに成功体験を味わってもらって、進んでいくうちに「4回目ぐらいで失敗させようかな」といった感じで設計するじゃないですか。そうじゃなくて、失敗も楽しい。スキーも谷底に落ちていってもいいじゃないですか。
田宮 でも一応、何をやるかまったくわからないのも困るので、一応ふわっとした目的を設けるのですが、過程が楽しいように設計しています。
——まさにそうですね。「アーガイルシフト」も発進シーンだけでワクワクしますし、「トレインマイスター」もまず電車の運転席に座ってる段階で満足度が高いです。
田宮 本当に好きな方は、「別にスタートしなくていいです」と運転する前の乗って眺めまわすところだけでだいぶ楽しまれていました。
小山 ちゃんと指差し確認したりね。
田宮 やってましたね。

JR山手線の運転手として業務を遂行する「トレインマイスター」。運転席がリアル。
ゲームセンターに外からイノベーションを
——収益面はどうでしょう? 一ヵ月先までかなり予約が埋まっているという大人気な状況もありますが。
小山 いや、まだ収支でいうと、そこまでではないです。
田宮 今はかなり潤沢にスタッフをつけて回しているところもありますし。
小山 筐体の置き方も贅沢じゃないですか。普通のゲームセンターでは、対戦台がびっちり並べられていて、その隙間を一生懸命通って筐体の中に入るようなところもあります。
田宮 われわれはできるだけゲームセンターに見えるような状態にしたくなかったんです。ゲームセンターと言ってしまうと、「じゃあ100円でプレーできますか?」という話になってしまいますが、それを一度リセットし、エンターテイメントとして新しい価値を提案したかった。
それがうまくいって、儲かる人が出てくれば参入が相次ぐし、もっと潤っていけばVRの産業としてもどんどん大きくなっていくと思っていました。その先陣を切る感覚があったので、あまり低い値段はつけれないなと。だから挑戦的な価格設定にさせていただいて、お客様がはたして受け入れてくれるのかというのも同時に見てみたいところがありました。
小山 VRの世界にはいる入場料なんですよね。「プレー」とか「ゲーム」という言葉を本当に取りたかった。その辺の人を捕まえて、「ゲームセンターってどういうもの?」と聞くと、だいたい「UFOキャッチャーがあって、奥にコイン落としがあって、あとはプリクラかな?」と答えるはずです。ゲームセンターって自分たちが子供の頃は最先端の楽しい遊び場だったんですが、今は「戦場の絆」を出した頃から10年間イノベーションが起こっていない。
2000年に施行された新大店法(大規模小売店舗立地方)でショッピングセンターが駆け込みでてきてしまって、一緒にゲームコーナーの出店ラッシュも起きたんです。そのときに各社がプライズ、メダル機、プリクラ、データカードダスを開発するようになって、気付いたらゲームセンターの中身が全部同じになってしまった。あとは力を入れるなら音ゲーですが、それも新しいものをリリースしても売り上げはそう変わらない。
だからゲームセンターにVRが入るのではなく、あえてその外につくることで、業界で新しいことをやっている人たちも刺激していきたいです。
田宮 「テーマパークなの?なんなの?」と一言で表現できない存在になれれば新しいんだろうなという意識はあります。ぜひご予約の上、遊びに来てください。
小山 お待ちしております。
©2016 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(TEXT by Minoru Hirota)
●関連リンク
・VR ZONE
・バンダイナムコエンターテインメント
・ナムコ