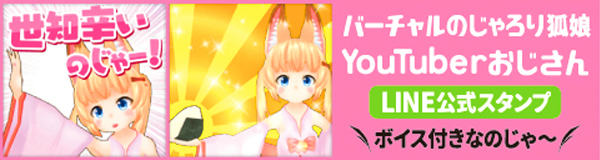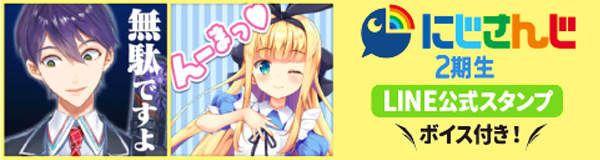講談社、ポリゴン・ピクチュアズ、ランティスが挑むVRの壁──「Hop Step Sing!」奮闘記(前編)

Hop Step Sing!のキービジュアル。左から箕輪みかさ(CV.日岡なつみさん)、虹川仁衣菜(CV.指出毬亜さん)、椎柴識理(CV.鳥部万里子さん)。
8月23日、講談社はVRアイドルプロジェクト「Hop Step Sing!」の第1弾楽曲となる「キセキ的Shining!」の360度動画をYouTubeにて公開した。同時にフルバージョンのアプリもAndroid向けにリリースしている(ニュース記事)。そして先日の東京ゲームショウでもHTCブースなど3カ所に出展し、その存在感を大いに示していた。
日本のVRコンテンツというと、「ユニティちゃん Candy Rock Star ライブステージ!」や「VR CRUISE」アプリに収録されている「初音ミクVR SPecial Live」といったGear VR向け作品、PlayStation VRのローンチタイトルである「初音ミク VRフューチャーライブ」など、キャタクターのライブがひとつの定番だ。
Hop Step Sing!は、ある意味、日本のお家芸ともいえるこのジャンルに、多くのキャラクターを世に送り出してきた講談社が真っ向からぶつかっていく挑戦と言える。
実際にコンテンツを視聴してみると、まずビジュアル面で惹きつけられる。自分がステージに座り、3人のキャラクターが目の前で踊ってくれる周囲で、360度の演出が入ったりと見所が満載だ。この制作はポリゴン・ピクチュアズが担当し、映像プロデューサーとして「シドニアの騎士」の石丸健二氏が起用された。
そこに耳に残る楽曲が加わる。作詞・作曲は竹達彩奈さんの「Hey!カロリーQueen」などを手掛けている「やしきん」氏で、音楽プロデューサーは「ラブライブ!」や大橋彩香さんなどを担当するランティスの木皿陽平氏。3人の声優さんの声のかわいさが絶妙に引き出されていることもあって、なんどもリピート再生したくなる。
このプロジェクトはどういった流れで強力な製作陣を引き込んで、何を目的に進んでいるのか。先の石丸氏、木皿氏に、講談社で本企画をプロデュースする松下友一氏を交えて、プロジェクトを振りかえっていただくと、大ヒット作を生み出してきた才能でも、VRという大きな壁にぶち当たって、悩み抜いたことがわかった。1万字オーバーの長文となったため、前後編に分けて余すことなくお届けしよう。

左よりランティスの木皿氏、講談社の松下氏、ポリゴン・ピクチュアズの石丸氏(以下、敬称略)。
OculusよりUnityのインパクトが強かった
——Hop Step Sing!の企画はどこからスタートしたのでしょうか?
松下 まず大きな流れとして、紙媒体以外のエンターテインメントコンテンツにも取り組んでいこうという方針が講談社にあります。それでデジタルでキャラクターを創出するために、2年前に企画が立ち上がって、当初はスマートフォンアプリで出す予定でしたが、制作単価がすでに跳ね上がっていて気軽に参入できない状況だった。じゃあどこでチャレンジするかと悩んでいたところに、VRに注目したわけです。
——割と最近、VRを体験して感銘を受けた感じでしょうか?
松下 いや、最初のVR体験はかなり遡った小学生の頃で、科学館でVRゴーグルをかぶったことをうっすら覚えています。ポリゴン数は非常に少ないですけど、バーチャル空間の中で自分の手を動かせたような。それからずっと技術は追いかけていて、ようやく今度のVRブームは本物かもしれないと感じています。
——「本物かも」と感じたのは、Oculus Riftきっかけでしょうか?
松下 OculusよりUnityのほうがインパクトが強かったです。基本的に無料で使えて、中学生だってお父さんのパソコン使えばVRコンテンツをつくれてしまうわけです。ちょうど20年くらい前のインターネットで起こった、お父さんのパソコンでWindowsに挑戦してたらホームページができちゃったというのと同じで、技術の民主化が起こっている。これはいよいよ本物かもしれない、と。
——おお! しかし、この強力な製作陣はどうやって集めたのでしょうか?
松下 企画としては、まずアイドルというキャラクターがもうありました。そこから人づてに相談したところ木皿さんをご紹介いただいて、「いきなり最強キター!」と(笑)
——(笑)。木皿さんは、突然話が振られてきた感じだったのでしょうか?
木皿 昨年に「お願いしたいことがある」とお話をいただいたのが、この企画でした。当初はVRありきではなく、ウェブコミックを連載しているというもう少しぼんやりとした状況でした。少し時間が空いてから、今年2月に「状況を整理したい」と講談社さんに呼ばれていったら「VRにします」と言われて。
音楽業界というと基本的にテクノロジーやインタラクティブとは無縁の世界なので、今まで仕事としてVRに絡んだことはなかったのですが、僕自身はイノベーションの中にできる限りいたいという思いです。今、アイドルものは増えていますが、その中で比較的古い段階から「ラブライブ!」という作品に携わってきていて、率直にVRで実際にキャラクターが近くにいるように感じられるのは面白そうでいいなぁって。
——確かに近さを感じられるのはVRならではの表現ですね。ビジュアル面をつくられているポリゴン・ピクチュアズさんが関わられたのはどのタイミングからですか?
石丸 ランティスさんよりあとで、今年2月頃に最初にVR用の3Dモデルをつくってほしいという相談があったんです。Twitterで1日1回配信しているウェブコミックを元に、Unityで動くモデルをつくってくれないかと。もともと松下さんとはアニメ「シドニアの騎士」でご縁がありました。
松下 月刊誌「アフタヌーン」の編集者で、シドニアのアニメにも関わっていたんです。
石丸 そのときのプロデューサーが私だったこともあって、軽い気持ちで「わかりました」と。VRは私も非常に興味があって、別案件でも使っていたリアルタイムエンジンで新しいことをやりたいという気持ちがすごく強かった。
──しかし、相談が2月頃で7月のUnity VR Expoで披露していたということは、半年ぐらいで終わらせた感じなんですね。

Unity VR Expoでの展示の様子。
石丸 実はアプリの話はもっと後で、モデルができあがった5月頃に「アプリを出したいんだけど」と相談されて、「マジか!?」と(笑)
——かなり急だったんですね。しかしVRじゃなくても、キャラクターライブのアプリを無償配布ではなく、販売するというのはかなり珍しい気がします。
木皿 キャラクターものでは、まだあまりないはず。
松下 VRのキャラクターライブでは、PlayStation VR向けに初音ミクやアイドルマスターが発表されていますが、いずれもすでに人気のあるキャラクターのVR対応ですから、VRでいちからキャラクターを立ち上げたのはまだ珍しい部類に入ると思っています。なので予算もかかっていますから、長く取り組むコンテンツにする意志を表明したいという側面もあります。
木皿 昨今のコンテンツでは、海外展開というのは非常に重要な要素になります。日本国内だけでなく、海外も意識したものにしないといけない。文化的な違いで、日本では受け入れられても海外では受け入れられなかったりするものもたくさんあると思います。ただ、VRなら海外に向き合ってつくれるタイミングなのかなと思います。
アメリカ・ボルチモアでのHop Step Sing! VR映像体験会、びっくりするほど盛況で1日目終わりました(こちらは今12日20:40です)。皆さん体験した後にすごく笑顔! 明日明後日もたくさんの人に楽しんでもらえそうです。 pic.twitter.com/vC7MYkB4D9
— Hop Step Sing! (@hopstepsing) August 13, 2016
この8月には米国ボルチモアで開催したオタコンにも出展してきた。
「フレームがない中、どうフレーミングするか」
——その視点は非常に興味深いです。制作にあたって一番苦労したところは?
松下 全部です。とにかく今までのアニメの演出技法がすべて使えない。じゃあどうしようかと悩んで、最終的にはバレエやサーカスなど、舞台で戦っている人たちを参考にしようという話になりました。ただ、僕は外野から「もう少しシルク・ドゥ・ソレイユ感だしてくれませんか?」とか無茶なオーダーしか出してなかったので、現場の石丸さんが苦労されたと思います。
——現場ではどんな感じでしたか?
石丸 私もフレームのある映像をつくることに慣れ親しんでいて、やはり360度見える空間の中に入っているという感覚での演出をやったことがありませんでした。かなり試行錯誤していて、正直いうとこのコンテンツも松下さんと反省している部分がたくさんあります。
やはり大きいのは、キャラクターを目の前にして、「枠」を隔てているか隔ててないかの差です。フレームのない中、どうフレーミングするか。最初はモーションアクターさんに踊ってもらったときに、「360度見られるんだからステージを広く使ったほうがいいのかな」と考えていたのですが、実はそれが効果的ではなかった。
——安易に360度に人を配置したり動き回る演出は、不自然だったり、VRゴーグルで見るときに首が疲れたりと、効果が薄かったりしますよね。
石丸 振り付けや演出を考える際、単純に人がいてセットがあってライブをやるというのではなくて、体験者の目となるカメラがどこにあって、カメラで見ている人が誰というところまでシチュエーションを落とし込んでつくらないといけないなと実感したんです。実はだいぶつくりこんだあとに、いろいろな方に見せてアドバイスをもらっていたのですが、体験者が置いてけぼりにならないようにシチュエーションを考えておいた方がいいと、Oculusの池田さんと近藤さんにアドバイスされて。
木皿 カット割りがつくれるって、すごくシネマティックなんですよね。動きが出て、メリハリがついて。でも、そこではない何かを模索しなきゃいけなかった。僕も最初見たときに「意外とステージが狭いんだな」と感じましたが、逆にあの距離感じゃないと間延びしてしまう。
石丸 音のバランスも、かなりできあがった最後の方で木皿さんに見ていただいて、わざわざリミックスし直してもらっています。
木皿 CD用に音をミックスした場合、2chで一番よく聞こえる形をとります。当初は3人の並びを意識して普段のCD音源を作る感覚でミックスしましたが、VRで見た際に立体感がないと、音の違和感が際立ってしまう。最初は「大丈夫ですよ」といわれて話で進めてましたが、せっかく360度聞けるわけで、その空間にいる感じはもっと出したい。
——立体音響は今回、使っていないですよね?
木皿 使っていないですね。ただその中でも、奥行きや高さはミックスし直しています。
——執念ですね。制作にあたって、どんなコンテンツを研究されたのでしょうか?
石丸 最初に見たのがユニティちゃんのライブコンテンツ(「Unity-chan “Candy Rock Star”」)で、松下さんに「当然、先輩作品を超える体験を提供したい」と言われました(笑)
じゃあ、ユニティちゃんを研究してもダメだなと実写ものを探して、偶然キレキレのダンスですごくよくできた「フェアリーズ」というアイドルグループのPVをみつけたんです。こんな風にしたいと提案したら、共感していただいたので、モーションアクターさんには「とにかくキレキレであまりまねできないダンスで」とお願いしました。しかも同じ踊りでは面白くないので、3人が別々の振り付けで、バレエダンサーのような動きも取り込んでます。
目指したのは息づかいを感じるようなライブですが、まだVRならではの特質をうまく吸収しきれておらず、ステージを広く使い過ぎたり、カメラを置く位置が突き詰めきれてなかったりと、いろいろ苦労が多かったです。
——数々の実績がある石丸さんでも、やっぱり悩まれてきたんですね。
松下 講談社は何十年もキャラクターものをやってきた会社ですから、VRという技術が出てきたらキャラクターとどんな接点を持たせようかと考えるのは、そんなに突飛なことでもないと思います。僕自身もただのオタクなので、アニメ作品のライブに行くことがあって、そこで自分が一番うれしいのは、やっぱりアーティストが自分の前まで来てくれたときなんですよね。その興奮をずっと味わえたらいいなっていう。
アイドルのライブによく行く友達の話を聞いても、ステージ間近で観てこその醍醐味があるそうです。やっぱりすごいステージパフォーマンスを見たら、人って単純に感動するんだなって。じゃあVRでも間近ですごいものをお届けしてみようと。
——しかし現段階だと、ゼロからのキャラクターでVRに挑戦するよりは、3Dモデルもあってファンも付いてるシドニアのような有名タイトルでやったほうが有利なのでは?
松下 わたしの所属するキャラクターVRチームのひとつの目的として、先端技術とエンターテインメントの接点を探るというのがあります。ですが、先端であるがゆえにプロデュースサイドに十分な知見が溜まっておらず、そのポテンシャルをエンターテインメントの領域に上手く引き出せない可能性もあるわけです。
先生方から著名な作品をお借りし、そうした不本意な結果が出て関係がこじれてしまったら誰も得をしない。だから自分たちで責任を取れるIP(知的財産)でやるべきだという思いはありました。
——なるほど。
松下 講談社って、基本的にはまだビジネスとして確立するか怪しい時期から攻めに行っちゃう会社だったと思っていて。そもそもの成り立ちが、講談という面白おかしいお話を本にまとめる事業から始まっていますし、漫画がまだ今のようにメジャーな存在になる前から「週刊少年マガジン」を発行していた。グラビア印刷という技術が出てきたらヘアヌードグラビアを出しちゃうし(笑)。
こういう攻める社風のなかに連なりたいですし、第一歩はやはり自分たちで責任を取りたいと思ったんです。そしてもうひとつ、先端技術を活用するなら作品もいちから育ててみたいというのもあります。すでに伸びた作品を借りてくるのでは、新しいことにチャレンジする意味があまりない。
木皿 おっしゃる通り、版権モノは作家さんの作家性や権利を守らなければいけないがゆえ、しがらみも多いです。Hop Step Sing!では松下さんたちが原作を持っているので、その辺は楽ですよね。
松下 本心をいうと「アイドルマスター」や「ラブライブ!」がうらやましかった部分もあります。自分たちのキャラクターを自分たちでプロデュースしていくというのはディズニーと同じなわけで、その責任をとってみたかったんです。
©講談社
*後編に続く
(TEXT by Minoru Hirota)
●関連リンク
・公式サイト
・公式Twitter
・講談社
・ランティス
・ポリゴン・ピクチュアズ