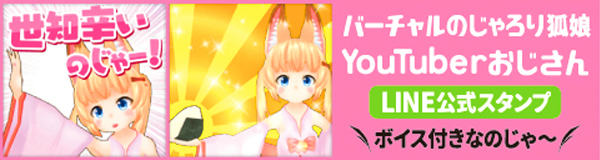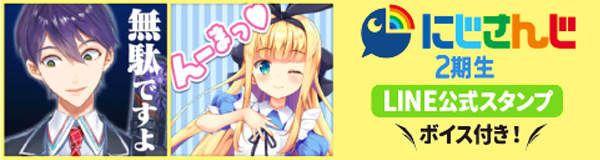電気おじさんたちはもういい──女性ファンが本当に喜んだ「ドリフェス!コール&レスポンスstage」の作り方

ナムコが24〜31日に東京・秋葉原の「アニON STATION AKIHABARA 本店」にて開催したバーチャルキャラステージ「コール&レスポンス Stage ドリフェス! 〜KUROFUNE ROCK な晩餐会〜」(レポート記事)。筆者も現地を取材したわけだが、キャラクターの存在感に非常に衝撃を受けた。
お客さんはサイリウムを振りつつ、壁のスクリーンに投影したバーチャルキャラと対話できる──というとなんだかビデオ上映会のような印象かもしれないが、現地の空気は真逆で、キャラクターがまさにそこにいるとしか思えない様子で、お客さんもステージとのやりとりに積極的に参加していた。
その理由はお客さんのキャラ愛はもちろんのこと、キャラの声を返すタイミングや内容が絶妙という点が大きい。一体、どんなチームがこのコンテンツを生み出したのかと取材すると、ナムコとバンダイナムコエンターテインメント、バンダイナムコ スタジオの存在が浮かび上がってきた。
というわけで、ナムコ IP営業本部エグゼクティブプロデューサーの相木伸一郎氏、バンダイナムコ エンターテインメント AM事業部VR部プロデューサーの鈴木直大氏、バンダイナムコ スタジオ VA統括本部 VA第2開発本部 本部長 プロデューサー/エグゼクティブサウンドデザイナーの大久保博氏というお三方に現地で直撃インタビューしたところ、「鉄拳」で培った技術もここに生かされているという話が浮かび上がってきた。非常に興味深い話なので、ぜひチェックしてほしい。
「ドリフェス!コール&レスポンスstage」は心のVR
──まず鈴木さんの肩書きが「VR部」というのが驚きました。バンダイナムコエンターテインメントさんにVR部ができたのはいつぐらいでしょうか?
鈴木 昨年10月からです。
──もう半年ぐらい前の話なんですね。ひょっとして今夏にオープンするという新宿のVR ZONEにも関わられていますか?
鈴木 そうですね。私も関わっております。
──そもそも今回のステージはどういったところから企画が始まっているのでしょうか?
鈴木 VRというとゴーグル型のコンテンツが目立っていますが、その既存の流れとは別に、ナムコさんと一緒に、キャラクターによるアトラクションに新しいアプローチができないかとずいぶん前から考えていたんです。
──キャラのライブというと、同じくアニONでVRゴーグルによる「ドリフェス!」ライブも行われていましたが、そことも関係が?
相木 あそこのチームとも連携はしています。
──そうなんですね! バンダイナムコグループのいろいろなVRの経験がこのライブにもつながっている。
鈴木 VR技術のアウトプット先はいろいろあり、その中のひとつのチームがわれわれになります。そもそも「VRとは何か?」という定義ってすごく難しいですよね。今回の「コール&レスポンスstage」については、ゴーグルを使わない「心のVR」と私は呼んでいます。
相木 ゴーグルをかけることだけがVRなのか、リアル感が出ていればVRなのか。そういう意味では、今回の「コール&レスポンスstage」もVRのひとつだと思っています。
──それはおっしゃる通りで、今回、お客さんとの対話によってキャラクターの実在感を際立たせていたアプローチが非常に興味深かったです。最初、普通のライブだと思って来たのですが、ほとんど会話のパートなことに驚きました。
鈴木 そうなんです。2時間の公演中、上演コンテンツは約50分。歌が3回あって1回あたり2分とすると、40分以上喋り続けてるんです。でもお客さんたちには、きちんと最後まで楽しんでいただけている。
──本当にびっくりしました。今までのバーチャルキャラのライブを取材してきて、割と会話のタイミングが合わなかったり、話してる内容が噛み合わなかったりでプレゼンス(その場にいる感覚)が剥がれてしまったことが多かったのですが、今回はほとんど感じませんでした。これってリアルタイムのモーションキャプチャーではないんですよね?
鈴木 はい、違います。しかし、会話のタイミング制御はきちんと手動で入れてます。

──手動! お客さんとの一体感も異常でした。このライブ自体は、別のところで似たようなものを開催したことがあって、予習していたんですか?
鈴木 われわれが知っている限り初めてで、台本もBNpictures(バンダイナムコピクチャーズ)の協力の元、書き下ろしですね。
──じゃあ本当に初見の状態で、あそこまでの一体感を作り出しているという。どういうことなんですか……!?
鈴木 CG映像を投影したライブというのはほかにもありますが、われわれが注力したのは「コール&レスポンス」、反応できるという点だったんです。「居るように思える」はすなわち「居る」。存在や認識とはなにか。バーチャルリアリティーはゴーグルがなくてもあるんだと。
相木 ただそこを実現するのがなかなか高度で、例えば「鉄拳」チームの技術などが入ってます。
──「鉄拳」が出てくるんですか。ここで!
鈴木 上演中、彼らがお客様の返答を待っているときにもピタッと止まらず自然に動きつつ待っている……という部分がありますが、例えばそこにも生かされています。また台本に関しても、例えばテレビや映画の素敵なストーリーなどとはちょっと違って、われわれはインタラクティブ性のあるゲームをずっとつくってきたので、その制作ノウハウを活用しています。
──その台本のみならず、タイミングもぴったりです。
鈴木 人力で操作していますので。ただその操作によるクオリティも、ナムコというお店のノウハウがあっての実現なんです。トークのときにどういうタイミングで、どう返事をするとお客様に喜んでもらえるのかというのは、電気の技術だけではできないことですよね。デジタルとアナログの両技術をまぜることができたからこそ、今回のような体験にまで高められたんです。
──それは以前、VR ZONEでも、案内してくれる店員さんの前口上があって、VRに対する警戒心が解けて没入感が高まるという体験をしたことがあります。
相木 われわれは普段、この会場でお客様と接していて、何を聞いたら何と返せばいいというノウハウが元々あるんです。
──この会場でも同様のキャラクターステージを過去にやったことがあるのでしょうか?
相木 キャラクターステージではなく、音楽を流して、MCの人がお客様としゃべりながら、みんなで大好きなキャラクターの映像を見るっていうイベントを毎日やっています。
──では本当にこの現場でのノウハウが、今回に生かされているんですね。
鈴木 そうですね。今回、ステージ機材も、レノボ・ジャパン、NECディスプレイソリューションズ、ヤマハの各社にご協力いただいて一級品を揃えています。バンダイナムコエンターテイメントの企画やプロデュースの力、ナムコの接客と店舗の力、そしてバンダイナムコスタジオの開発チームの技術力。この組み合わせを真似できるところはそうそうないと思います。

ファンが見たいのは、キャラの意外な一面
──クリエイティブディレクターを務めたという大久保さんは、どういった部分を担当されているのでしょうか?
大久保 はい。バンダイナムコスタジオは普段ゲームをつくっている会社なんですが、今回、3社でやりたい企画があって、この場所があって、どうします?という流れから、当社ではゲーム開発の技術を活かし、ストーリーの展開方法や操作側の仕組み、音響や照明演出などを提案した上で、開発を担当しました。
──制作で一番大変だった点は?
大久保 色々大変でしたね。
鈴木 「やろう」と言い出したのは確実に我々なんですが、イメージしたステージは未だ誰も見たことがないものだったんです。ゲームともちょっと違うから、まず台本はどうつくればいいんだとか、映像も音楽も何もかもが手探り続きでした。一方で、ビジネスなのでスピード感も重要で、見たことのないものをみんなで信じてがんばり続けてきたというのが一番大変だったところです。
大久保 まず実現したいものがあって、それを商品としてお客様に届けるパッケージに落とし込まなければいけない。ゲームを作るのと同じように開発に関しては大変な作業ですし、技術的な解決方法などもどうしようかと悩んだところもあります。
──投影装置としても、初音ミクのライブのように透明スクリーンを使う選択肢があったのでは? これはリアプロジェクター(背面からスクリーンに投影するプロジェクター)ですか?
大久保 いや、普通のプロジェクターです。
──あっ、一見わからなかったのでリアプロかと思ってました。

写真手前をよく見るとプロジェクターが置かれている。
鈴木 プロジェクターがむき出しだとお客さんの「キャラクターが居る感」を損なうので、ライブでよくあるアンプっぽく見えるように黒くしています。こういうところの積み上げが、単に企画を立てたり、ゲームをつくれたり、お店があったりするだけじゃない我々の「総合力」だと思ってます。
大久保 結局、全部ハイテクノロジーにすればいいというものでもないと思います。どうすればお客様が喜んでくれるのか。そして限られた時間の中で、自分たちが思い描いていることを実現できるのか。どんどん凝ったことをやっていけばいいというわけでもなく、生産性も考えてお客様が喜んでいただけるラインかどうかを判断してゆく日々でしたね。今回の「ドリフェス!」公演でも全部やりきれた訳ではなく、実は中身としても、操作性にしても、レスポンスにしてもまだまだよくしていける部分があるんです。
──しかし、話が戻りますが、なぜトークパートに台本の大半を割くという大胆な策をとったのでしょうか。
大久保 女性が本当に求めてるものって考えたときに、やっぱりキャラクターの意外な一面とか、このサイズのハコで見れる素顔を見たいのではないかと考えました。それをどう叶えるかとなると、歌だったら極端な話PVでも見れたりするわけで、意外な一面とか、かわいい一面を見たい。シナリオも実は何個か用意しているんです。
──えっ、何個かってことは、別の機会に来たら違う話をしてくれるという?
鈴木 はい、今日のはごく一部のバリエーションです。
──ひえーーー!
大久保 逆にこのような複雑なMC部分を作るよりも、歌のように時間や振付が決まっている部分のほうがつくりやすかったです。この仕組みのポイントは、お客さんの反応を見て話が変わっていくところですが、歌もあって総合的に楽しめる内容かと思います。
──公演名の「コール&レスポンスステージ」というのがその通りで、お客さんも一緒に場を作り上げているんですね。
鈴木 もちろん目論見はあったんですけど、これが実現できたのも合同チームでずっとやってこれたからだと思います。企画ができたから発注します、という距離感ではなく、みんなで走ってこれたのがここまでたどり着いた大きなところです。
相木 女性にジャッジしてもらっているというのも重要なところです。ゲームも映画もやっぱり男社会で、実は本当に女性が求めているものが提供できていないんじゃないかという不安もありました。
──女性に結構リサーチしたという?
鈴木 もちろんしましたし、制作自体も男が多いゲーム開発会社の中で、例えば、モーションキャプチャーのときは男3女7、打合せでも男女が半々といった感じで、女性の方が現場に多いというシチュエーションが何度もありました。よくわれわれの打合せの中でも、「電気おじさんたちはもういいんだ」とよく言っていたぐらいです。
──電気おじさん(笑)。
相木 おっさんをあてにしないで、女性目線で彼女たちがやりたくて、表現してほしいことを突き詰めようと。最後のクオリティーチェックも、完全に社内の女性です。
──彼女たちが満足したらOKっていう。
鈴木 電気おじさん達の、彼女らへの信頼感は凄いです。そうやって何とかここまでこれました。この「ドリフェス!コール&レスポンスstage」だけでなく、今後もさまざまなVRの取り組みを提案していくのでぜひバンダイナムコグループに期待していてください。
©BNP/BANDAI, DF PROJECT
(TEXT by Minoru Hirota)
●関連リンク
・公式ページ
・ドリフェス!公式サイト