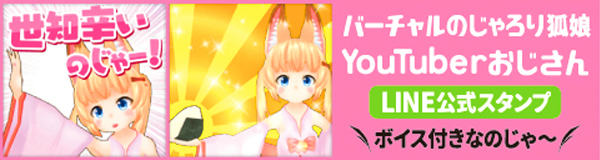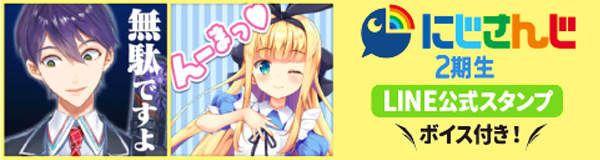【超会議2019】超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』の桜、吉野の桜 【特別寄稿:福岡俊弘】
桜が舞っていた。
2012年4月、僕たちは吉野山に登り、険しい斜面だらけの中に奇跡的に広がった平らな地面の上に寝そべって、ぼんやりと桜を眺めていた。谷間を埋め尽くすあまたの山桜。真っ白なインクを山一面にぶちまけたような、それでいてどこか淡い紅を被せたようなその景色に吸い込まれそうになりながら、思い思いに眼下に広がる壮大な桜色の絨毯を見ていた。吉野千本桜。時折強い風が吹く度に、花曇りの空から桜の花びらが舞い降りた。
「小説にできそうな気がする」
「物語はあるしね」
「挿絵、どんなのがいいかな」
『小説・千本桜』のプロジェクトはそうして始まった。7年前のことだ。

今年の超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』は本当に素晴らしかった。3年前の再演だろうと思って千穐楽の舞台に臨んだら、まったく違っていた。というか、歌舞伎そのものだった。
これまでの超歌舞伎も、もちろん毎年素晴らしいものだったのだけど、それはどこか“初音ミク”という文脈ありきで作られていたような印象だった。役者としての初音ミクの完成度、という尺度が作る側にも観る側にも厳然とあった。歌舞伎の所作、口説き、間合い。仮想のキャラクターはどこまで進化し得るのか、歌舞伎をエンターテインメントとして楽しむ前に、そんな命題を背負った浅葱幕を振り落とさなきゃいけない。無意識にそう感じていたように思う。
逆に言えば今年の超歌舞伎では、役者としての初音ミクは、自然な形で歌舞伎の中に取り込まれていた。何より、観客が歌舞伎の客であった。萬屋、紀伊國屋、初音屋のかけ声は会場中を揺さぶった。大画面の映像に頼りすぎることもなく、荒事の所作もクドすぎず、台詞のひとつひとつが物語を、浄瑠璃を構成していた。個人的には、クライマックスあたりで流れてきた義太夫節っぽい節回しの語りに痺れた。そして、中村獅童、澤村國矢ら歌舞伎役者たちの圧倒的なパフォーマンス。すべてが本物の“歌舞伎”だった。

Ⓒ WhiteFlame/一斗まる Ⓒ Crypton Future Media,INC.www piapro.netpiapro
『小説 千本桜』は、吉野山でのふんわりとした雑談からおよそ1年後、紆余曲折を経て、一斗まるさんが書き上げた。初版の発行日は2013年3月9日。発売日に増刷が決定するという驚異的な売れ行きだった。「重版出来!」ーー編集者なら一度はやってみたい宣伝文句が現実となった。この年、この小説の世界観が起点となって、上田城の千本桜祭のメインビジュアルに千本桜ミクが起用されたり、なんとニコニコミュージカル『音楽劇 千本桜』が上演されたりした。
「10年歌い継がれる、10年語り継がれるコンテンツになるよ、これ」
吉野の桜の下で、さほどの根拠もなく、黒うさPと一斗まるさんに熱くそう語った。7年後の今年、令和最初の年に、「千本桜」は本当に歌舞伎になった。しかもこの8月には京都・南座で本公演として上演されるという。本当に10年いっちゃうよw。さすがに、感慨深いという以上の言葉が出て来ない。
『小説 千本桜』を刊行した翌年、KADOKAWAを離れざるを得なくなり、「千本桜」と直接的な関わりができなくなった。メディアとしての「千本桜」のカタチがうっすらと見えてきたときだっただけに、無念というほかなかった。が、幕張イベントホールに舞った桜吹雪は、あのとき吉野に舞っていた桜だ。どこで見ようと桜の美しさに変わりはない。だから今は、『小説 千本桜』を世に出せたことをただただ喜びたいし、関わってくれたみんなに感謝したい。
京都に舞う桜が本当に楽しみで仕方がない。
(文 福岡俊弘/編集 松崎雪奈)

●関連リンク