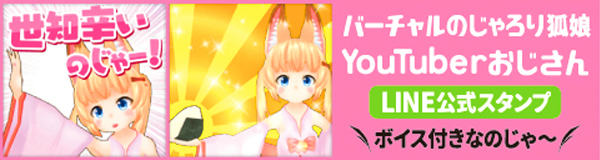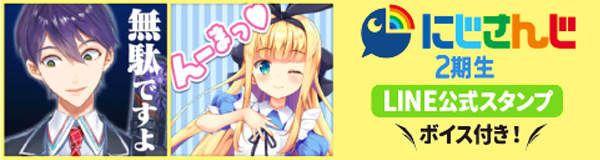VRで人を再現するには? サマーレッスン・アニメ制作チームの飽くなき挑戦(前編)

日本のVR業界において、ひとつ太いジャンルとして成長しているのがキャラクターものだ。ゴーグルをかぶってキャラを目の前にすると、テレビやスマートフォンとは違って本当にそこにいるように感じられるのがVRならではの強みなのだが、一方で何のノウハウもなく単純にキャラをVR内に出現させただけでは人としての存在感をうまく生み出せずに失敗に終わることもある。
VRで人を再現するには、何が重要なのか──。そんな難問に昨今のVRムーブメント初期から挑み続けているのが、バンダイナムコエンターテインメントがPlayStation VR(PS VR)向けにリリースしている「サマーレッスン」シリーズだ。
2014年夏、まだPS VRが「Project Morpheus」(プロジェクトモーフィアス)と呼ばれている時代に、女子高生とコミュニケーションができるデモ版の開発が明らかになると世界で注目を集め、あまりの話題にお披露目を東京ゲームショウから11月に延期するという伝説をつくった。
2015年のE3ではさらに金髪美女のデモを公開した上で、2016年10月のPS VR発売時には「サマーレッスン:宮本ひかり」がローンチタイトルとしてリリースされた。その後、2017年6月には第二弾の「サマーレッスン:アリソン・スノウ」を、そしてこの10月12日には「サマーレッスン:新城ちさと」と、まさに「VRでキャラ」の歴史とともに歩んできた存在といえる。
サマーレッスン:宮本ひかり(PS Store)。
サマーレッスン:アリソン・スノウ(PS Store)。
サマーレッスン:新城ちさと(PS Store)。
実際に体験してみるとその存在感や振る舞いに驚きを隠せないわけだが、そんな彼女たちはどういった手法で生み出されてきたのか。そもそもVRでキャラに命を吹き込むためには、何が重要なのか。シリーズのプロデューサーである玉置絢氏(写真右)に加え、アニメーション全体をディレクションした森本直彦氏(写真中央左)、モーションキャプチャー(モーキャプ)担当の深渡瀬美紀さん(写真左)、表情をはじめとするアニメーションをブラッシュアップした山下洋介氏(写真中央右)をお招きして、その秘密を明かしていただいた。
かなりの長文になったので、3回に分けてお届けしよう。
●前作のインタビュー記事
・実写の撮影手法でVRのPVをつくった 玉置Pが語る「サマーレッスン:アリソン・スノウ」への道(前編)
・今回のテーマは癒し!! 玉置Pが語る「サマーレッスン:アリソン・スノウ」への道(中編)
・透き通る金髪の再現を見てほしい 玉置Pが語る「サマーレッスン:アリソン・スノウ」への道(後編)
予算も時間もない中でのデモ版制作
──まずサマーレッスンシリーズにおけるみなさんの担当を教えてください。
深渡瀬 私は顔、身体のモーキャプを収録してデータをブラッシュアップし、アニメーターへ渡すという最上流の工程を担当しています。
森本 僕は肩書き的にはサマーレッスンのモーキャプのディレクターという立場です。アニメーションに関わる部分全部の責任者というか、玉置の要望に応じて具体的にどうやってつくっていくかを決めています。もちろんオーダーだけでなく、現場に立ち会ったりもしています。
玉置 私から見ると森本さんには3つの顔があって、1つ目は私たち企画陣がやりたいことをうけて、具体的にどういう風に落とし込むかを提案してくれるアニメーションディレクターとしての立ち位置。
2つ目は全体の進行の中で、今回の予算と時間だとこれくらいの量のアニメーションがつくれますが、こういう風なことをしたらもっとコストを下げられるかもと相談して、実際に作業が始まったら「あと何日以内にこの台本がないとダメですよ」と、アニメーションのプロセスマネージメントをしてくれる立場。
最後が、モーキャプのデータをMaya上だけでなくUnreal Engine(UE)上でもいじって、サマーレッスン特有のインタラクティブ部分まで調整してくれる、アニメ担当とエンジニアの中間的存在、2セクションの間に立ってプログラマーの窓口にもなってくれるという立場です。
──ものすごく何でもやる人ですね。
森本 そうですね。今までにないようなジャンルなので、目的のためには何でもやるみたいな感じです。
──山下さんは?
山下 基本的には顔のアニメーションの担当で、キャプチャーしたデータをUE上で仕上げる仕事です。
──そんなみなさんが手がけられてきたサマーレッスンの仕事で、まず話しやすそうな一番大変だったことをお聞かせください。
玉置 それは技術デモと製品版の時代で違うタイプの苦労があったから、その2種類を話すのがいいかな。
──ゼロからつくった技術デモの苦労はどうでしたか?
森本 大きかったのは、とにかく時間がなかったということですね。
山下 デモ版では「時間ないからか待ってらんねぇ!」って、ピーキーなつくり方をしたので、後で誰もデータが触れない状態になってました。突貫で、もうフェイシャルリグ(表情付けのためのコントローラー)とかも作っている時間がなくて「そんなものいらねぇ」って、ボーンを直接いじってアニメーションつけていたので。
──(笑)。デモ版の制作発表は2014年の夏でしたよね。
森本 そうです。
──それで話題になりすぎて東京ゲームショウでの展示をスキップして、初めて一般公開されたのが2014年冬だった。その間に急仕上げで作ったみたいな?
玉置 いや、制作の中心となった時期は2014年の春からの2ヶ月間です。そこからお披露目した秋までは、チームを半解散させて残ったプログラマーだけで最適化対応などをしていました。元々、製品化する予定はなかったので予算が限られていて、そうなると人件費の関係で短い時間しか稼働できない。実際、全員がサマーレッスンの専門じゃなくて、森本さんも違うプロジェクトから一時的に来てもらっていました。山下さんも「バンナムが変な事をやるので、2ヵ月くらいだけいてくれない?」という感じできてもらったという、急ごしらえのチームだったんです。

2014年冬の体験会の様子。
──本当に時間がなかったんですね。
玉置 そうですね。
森本 とにかくPS VRが何なのかもわからない。世の中の人が見たことないですから。
──当時はProject Morpheusという名前でしたし。
玉置 VRで何がお客さんに刺さるかもわからない時代でした。
森本 そんなわけで予算枠としても優秀なスタッフを長期間専業で担当させる余裕がなかったので、限られた期間でやれるところまでやるという感じでした。
何も考えず100%人間を再現しようとしたら気持ち悪くなった
──当時、みなさんがVRを体験されたのはOculus Riftの初代開発キット(DK1)だったのでしょうか?
森本 VRという意味ではDK1が最初です。僕なんかは本当にVRを知らなくて、でもつくるっていうことになったので、いろいろ試して立て続けにMorpheusのコンテンツも体験しました。

2013年にリリースされたOculus RiftのDK1。
──そうしたいろいろ体験された中で、「この表現がやりたい」という目指すものはありましたか?
森本 すごく初期だったので、ジェットコースターのデモなど、とにかく体験できるものが限られていて、キャラクターがプレイヤーに対して本格的に何かしてくれるコンテンツは存在しなかった。それを玉置くんやりたいという話だったので、世の中になかったものをどうやって形にしていくかが一番大変だった記憶があります。
玉置 お手本となるのは現実しかなかったっていうことですね。現実の人間っぽいものをつくるっていうので、アニメーションでも人間っぽく見せるところが大事になる。だから表情のキャプチャーを強化したり、アニメーションもより丁寧につくらなければいけない。
そういったクオリティを担保するための人は揃ったけど、「それでどうするの」というところからが本当の戦いで、VR空間でキャラが近づきすぎたらのけぞるとか、動いたものを目で見るとか、そういった仕様を研究していくうちに、再現しなければいけない要素がだんだんわかってきたんです。
──同じモーションでも、普通のゲーム用とVRでは違うものなんでしょうか。
山下 そうですね。基本的にサマーレッスンで使っている技術は普通のゲーム制作の延長線上にありますが、最初の頃に感じたのは、今までコンソールゲームをつくってきた感覚からするとプレイしたときのディティールへの感度が二段階ぐらい上がるということなんです。モニタ画面の先にいる顔として見てる分には許容できるようなちょっとした部分も、VR空間内の目の前にいると気になって仕方がない。
──具体的にそれを感じられたシーンはどこでしょう?
山下 一番大きなところでは、目線がぴったり自分に合ってない違和感です。一応、カメラに視線向ける指示は出していますが、それがシビアで少しずれただけでもとたんに気持ち悪く感じてしまう。目の動きひとつとっても、人間の目って絶対に止まっていなくて、細かく眼球振盪(がんきゅうしんとう)しているので、眼球が完全に止まっているのが本当に気持ち悪い。

──深渡瀬さんや森本さんも似たようなことを感じられました?
深渡瀬 そうですね。VRが始まる前までは、フェイシャルキャプチャーでそこまで細部にこだわるものはなかったように感じます。クオリティーへの要求が高いと感じました。
──やっぱりこうインタビューしてても顔と目を見ますよね(笑)。それはVRでも相当こだわらないといけない部分という。
森本 でも一番最初のひかりちゃんができたときは、ほぼ100%人間を再現したんです。そうすると逆に気持ち悪くなってしまった。
──えっ!
森本 可愛いCGのキャラクター女の子が笑った時に人間の顔とまったく同じにするとダメだということがわかったので、キャラ性を強調することになりました。
サマーレッスンには宮本ひかり、アリソン・スノウ、新城ちさとと3人のキャラクターがいますけど、それぞれやってる役者さんとキャラの子はやっぱり違うわけです。笑ったときはこんな風というキャラの特徴を、ちゃんとわかってないと、「何か違うな」と違和感を感じてしまう。
玉置 いってみればVRはまだ途上のぎ技術で、現実を100%そのまま再現することはできないんです。コンピューター自体や表示装置の能力で限界があるので、それを埋めるために何らかの記号性を付けてディフォルメしなければいけない。
──その考え方は非常に興味深いです。
玉置 もう1つ、順番的には人間っぽいものをつくるという意識があったうえで、可愛くないと意味がないと追求していたのですが、VRではどれだけ可愛さを追求しても人間ぽくみえないと「人間じゃない何かよくわからないものが可愛い」にしかならないんです。だから、人間として隣にいても警戒しなくていい、安心できるっていうものも同時に追求しなければいけない。それがわかってきたのが、デモ制作のときでした。
──やっぱり近くにいたいと思わせる必要があるという。
玉置 「隣にこの人いてほしくない」って言葉をよく聞きました。最近で言えば、ちさとちゃんの前髪が鉄拳のリリやアンナのような完全なパッツンで分け目がまったくないデザインだったときがあって、それをVRで見るとすごく怖かったんです。それで目つきもキツい。テレビの向こうの芸能人として見る分にはいいけど、隣にいたら話する気になれなかった。
デモ版制作の当時も同じで、表情などで人間っぽく見えないところがあると、隣にいても「自分はCGの世界に訪れたんだ」という異邦人な感覚が抜けないんです。それを失くすのがすごく大変でした。
──話を聞いてると、接客業の接待モードじゃないですが、素の人間としてゲームの中に出てくるのではなく、意識して好かれるようなデザインに作らないとダメみたいな感じでしょうか。
玉置 そうですね。人に好かれる振る舞いがつくり込めているかどうか、そういう採用試験みたいなところはあります。
──それはモーションの元となる声優さんの採択にも影響があったりしますか?
玉置 いや、キャスティング時にそこまで考えていられるのは本当に最後の方の話で、デモ制作時は全然そんなことはなかったです。宮本ひかり役の田毎さんがこのゲームのコンセプトに合ったキャストだったと分かったのも開発してみたあとの話で、キャスティングの運がよかったのとご本人の努力によるところが大きいです。とにかく時間も、お金もそんなに好き放題できるわけではないというのが先でしたね。
──デモ版の大好評があったうえで、製品版をつくることになった際には、スケジュールや予算に余裕はでてきたのでしょうか。
玉置 そうですね。そこでじゃあ製品版とデモ版で何を変えるかっていうのも考えなければいけなかったし、さらに人をどうするかっていう話もありました。
──人?
玉置 「VRの中で人間をつくれる能力があるクリエイター」という基準が世の中にまだいないわけですよ。そんな教育はどこでもやっていないわけで、われわれが知ってる範囲ではサマーレッスンのデモ制作経験者しかいなかった。それで森本さん、山下さんを製品版でも引き続きお願いできるかどうかが鍵になりますと。
──サマーレッスンチームに引き抜いたという?
玉置 そうですね。日本で唯一、下手をしたら世界でも唯一、アニメと実写の中間っぽいキャラで、人間っぽく見せる、錯覚させるというノウハウ持ったクリエイターを揃えなければと。
そこからマスプロダクション、量をつくらないといけないわけです。サブキャラをあわせると、数時間分くらいアニメーションをつくっていて、RPGのムービー部分と比較しても長いわけです。その目的を実現するのに社内にスタジオも用意して、優秀かつ非常に歴史のあるモーションキャプチャーチームがあるので、深渡瀬さんにも加わっていただき、3人で技術デモから製品にどう発展させるかと試行錯誤していった感じです。
*中編はこちら
(TEXT by Minoru Hirota)
●関連リンク
・サマーレッスン
・バンダイナムコエンターテインメント
・PlayStation VR